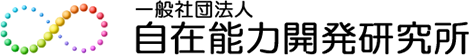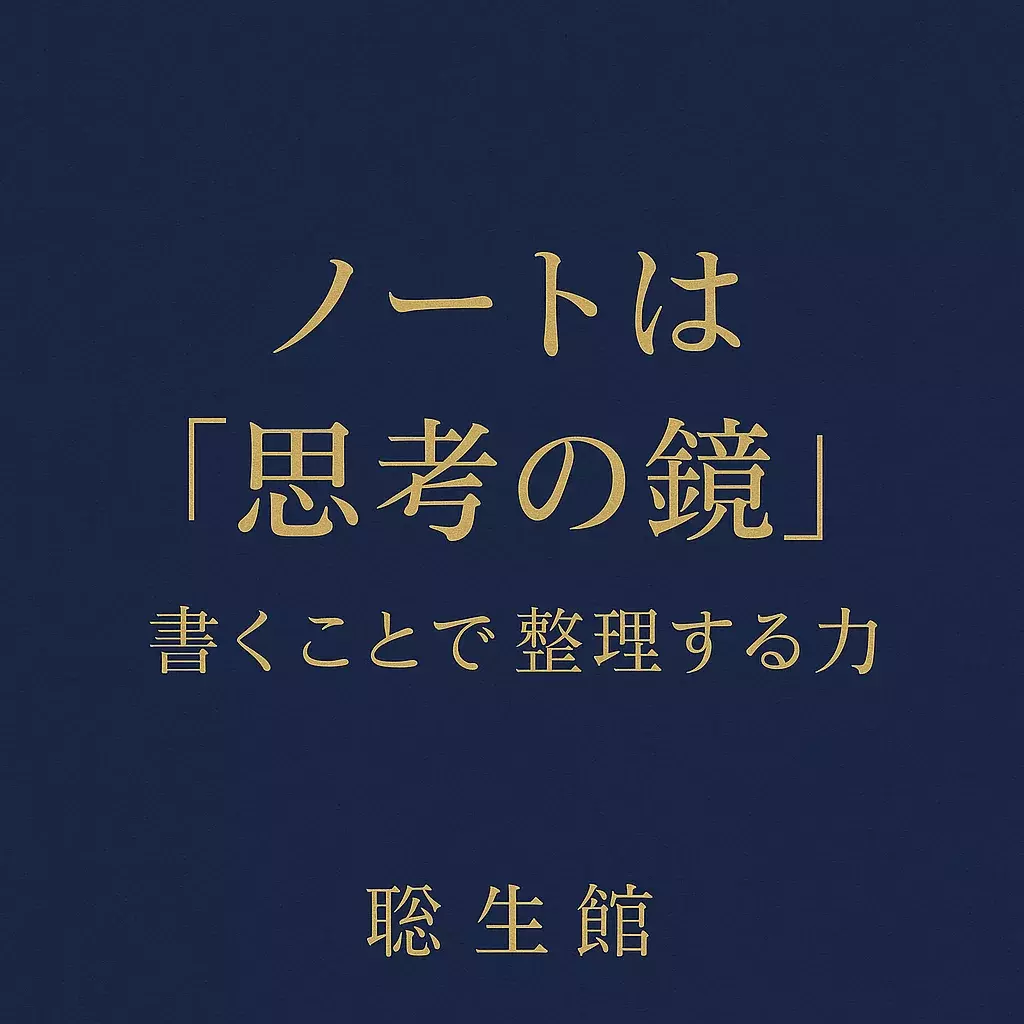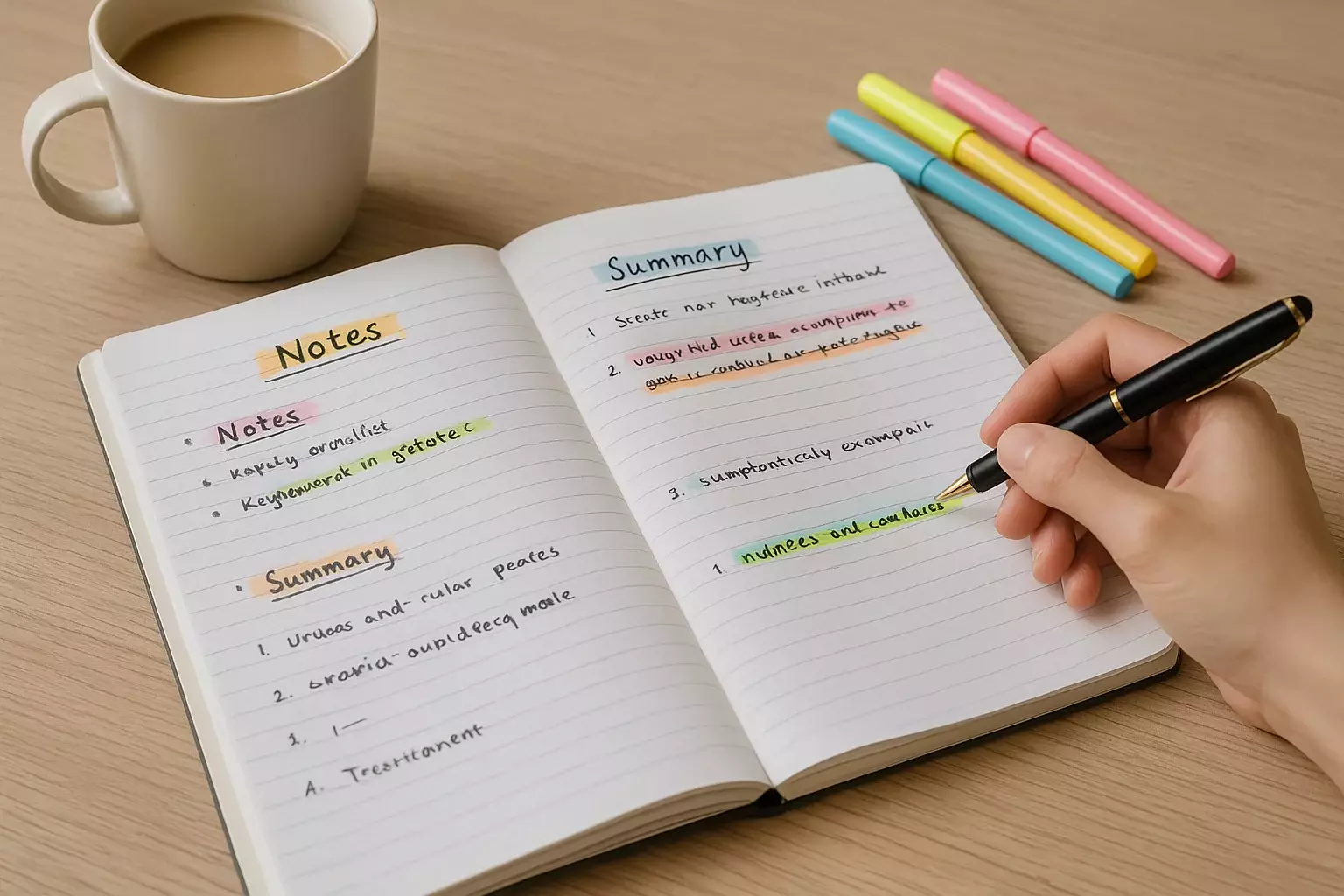学力・人間力向上のためのブログ
-
2025/10/22
🌱 ノートは“こころの記録帳” ― 自分の成長を見える化する
1.ノートは「思考の鏡」であり、「心の記録帳」でもある
スプラウツの教室には、子どもたち一人ひとりに専用のノートがあります。
そこには、計算式や漢字の練習だけでなく、日々の気づきや感情のメモ、時にはイラストや色で表現された“心の記録”が残されています。
ノートは、ただ勉強の内容を書き留めるだけのものではありません。
**「今の自分」を見える化するための“こころの記録帳”**なのです。
私たちはつい、結果や評価ばかりを見て「できた・できない」と判断しがちですが、
実際にはその途中のプロセスこそが、子どもたちの成長を語る何よりの証拠です。
ノートには、その「成長の軌跡」がしっかりと刻まれています。
2.“書く”ことが心を落ち着かせる
スプラウツでは、不登校や発達特性をもつ子どもたちにとって、
「書く」という行為がとても大切な意味を持つことを実感しています。
ノートに文字や言葉を書くことで、頭の中が整理され、心が少し落ち着く。
思考と感情を外に出すことは、心の中の渦を整える行為なのです。
たとえば、焦りや不安でいっぱいの子どもが、ノートに今日の出来事を書き出してみると、
「意外と大丈夫だった」「少し前よりできるようになった」と気づく瞬間があります。
その瞬間、子どもは自分を少し肯定できるようになります。
ノートは、そんな「心の安定剤」のような存在でもあります。
3.“振り返る”ことで成長が見える
スプラウツでは、子どもが書いたノートを定期的に一緒に見返します。
そこには、最初はうまく書けなかった字や、途中でやめたページ、そして次の週にもう一度挑戦した跡などが残っています。
「このときは疲れていたね」
「でもここではすごく集中できてるね」
そんな対話を通じて、子ども自身が自分の成長を客観的に見られるようになっていきます。
ノートを開けば、「あの日の自分」がそこにいます。
それを見つめ直すことで、子どもたちは少しずつ「自分の力を信じる」ようになります。
4.“できない”を“できる途中”に変える
ノートの中には、間違いや書きかけのページもたくさんあります。
でも、スプラウツではそれを“失敗”とは呼びません。
「ここはまだ途中だね」
「このページから、次の発見につながるね」
そう語りかけることで、子どもは自分の努力を否定せずに受け止められるようになります。
**ノートは「失敗の証」ではなく、「挑戦の証」**です。
書きかけの文字も、消しゴムで消した跡も、その子が“考えた痕跡”として残しておく。
それが、スプラウツ流の「見える化」です。
5.“こころのノート”の使い方
スプラウツでは、通常の学習ノートとは別に、
「こころのノート」と呼ばれる記録帳を活用しています。
このノートには、次の3つの項目を日々記入します。
1️⃣ 今日の気分(○・△・×などで簡単に)
2️⃣ 今日の学び・気づき(短い言葉でOK)
3️⃣ 明日へのひとこと(希望や目標など)
このたった3行の習慣が、子どもの“自己理解”を大きく変えていきます。
とくに不登校や心が不安定な時期には、「昨日より一歩進めた」「今日は休んだけど、明日は書けた」――
そうした変化を記録として残すことで、子どもが自分の力を実感できるようになるのです。
6.“見える化”がもたらす自己肯定感
人は、自分の頑張りを“見える形”で確認できると、自然に前向きになります。
これは、心理学でも「達成の可視化効果」と呼ばれる現象です。
子どもが自分のノートをめくるとき、
「ここまでできた」「これも書いた」「前よりきれいに書けるようになった」――
そんな小さな成功体験が積み重なります。
この“見える化”が、自己肯定感を回復させる力になります。
スプラウツでは、ノートを「評価」ではなく「承認のツール」として扱っています。
書くことで自分を知り、見返すことで自分を肯定する。
それが“こころのノート”の本当の価値です。
7.先生のコメントが「未来へのメッセージ」になる
スプラウツのスタッフは、子どものノートに短いコメントを添えます。
「よく頑張ったね」「この部分の考え方がすてき」「次はここを一緒に考えよう」
そうした一言一言が、子どもの心を温め、モチベーションを支えます。
コメントを書くときに意識しているのは、“過去の努力”を認め、“未来の可能性”を信じる言葉をかけること。
「やればできるよ」ではなく、「ここまでできたね」。
この違いが、子どもの心の受け取り方を大きく変えます。
ノートに書かれた先生からの言葉は、時間が経っても残ります。
だからこそ、ノートは“心の対話帳”でもあるのです。
8.「書く力」は「生きる力」になる
“書く”という行為には、集中・構想・表現という3つの思考過程が含まれています。
それはまさに、「自分の考えを形にする」練習です。
不登校やひきこもりの時期には、言葉にできない思いが心の中にたまります。
その思いを少しずつ言葉に変え、ノートに残すこと。
それが、心を回復させ、再び社会とつながる第一歩になります。
子どもが「自分の感じたこと」を書けるようになったとき、
それはすでに“再出発”が始まっているサインなのです。
9.「ノート」は時間を超える宝物
スプラウツでは、卒業する子どもたちに「最初のノート」を返しています。
そこには、迷いながらも懸命に書いた字、先生のコメント、途中で止まったページ、
そして、再び歩き始めた記録が残っています。
それを手に取った子どもたちは、必ずと言っていいほど笑顔になります。
「これ、最初のころの自分だ」「あの時、頑張ってたな」
ノートは、時間を超えて“成長の証”として残り続けるのです。
10.おわりに ― 書くことで、心は動き出す
ノートは、静かに語りかけてくれる存在です。
「あなたは、ここまで歩いてきたよ」と。
スプラウツでは、今日も子どもたちが自分のペースでノートを開き、
一文字一文字に“今の自分”を刻んでいます。
その小さな積み重ねが、やがて大きな自信となり、
未来を描く力へと変わっていくのです。
ノートは、知識を写すためのものではなく、
“自分を写すためのもの”。
そして、ページをめくるたびに、子どもたちは自分の心の成長を見つめ直していきます。
Category
カテゴリー
Archive
アーカイブ