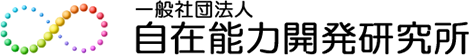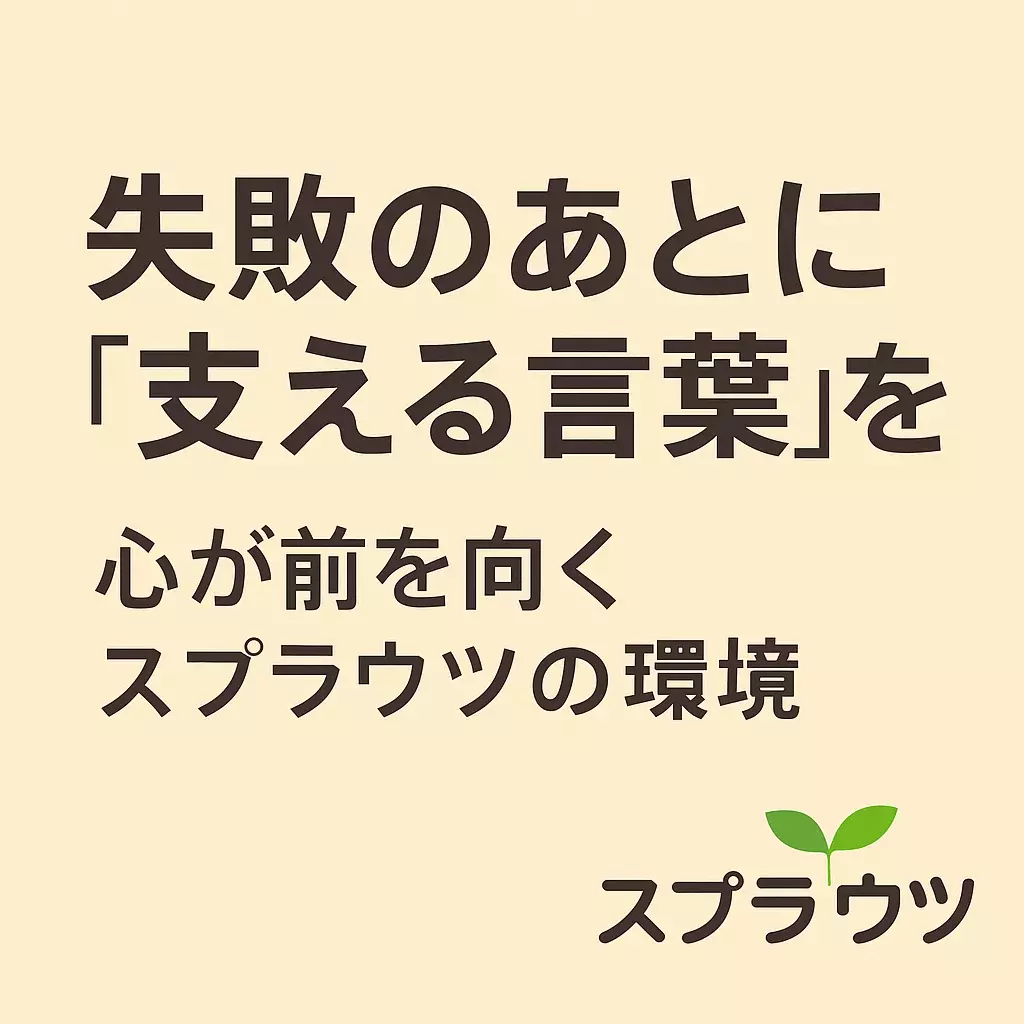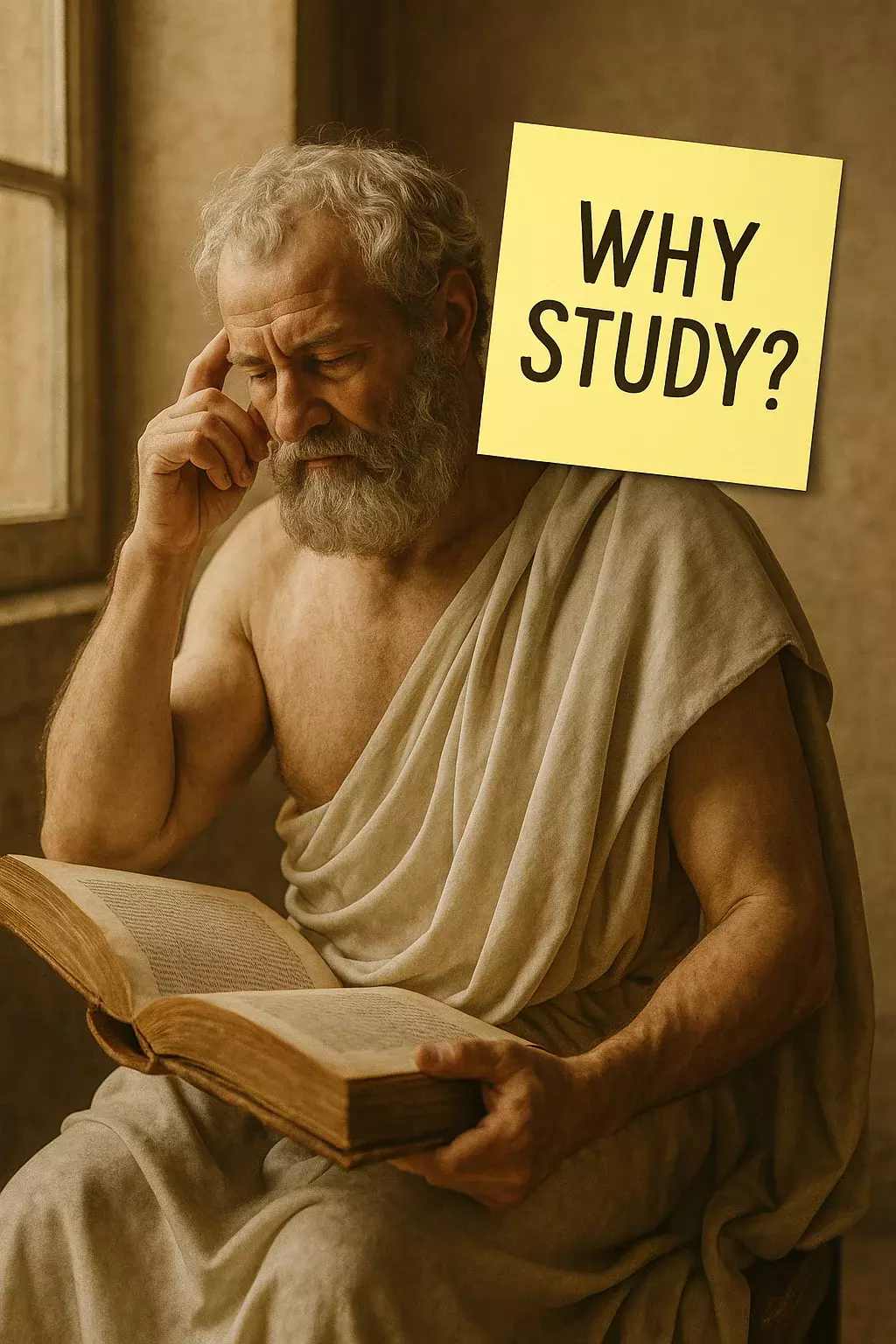学力・人間力向上のためのブログ
-
2025/10/12
AIが“共感”を量産する時代に、人間の言葉はどこへ行くのか ― 聡生館が考える、教育と言葉の未来 ―
AI(人工知能)が文章を作る時代になりました。
SNSや広告、教育分野でも、AIが人の感情に寄り添うような「共感の文章」を生み出すことが増えています。
確かに、AIの言葉は優しく、読みやすく、そして整っている。
しかし、その完璧な文章を目にすると、私たちはふと考えます。
――「人間の言葉」は、これからどこへ行くのだろうか。
この問いを、私たち聡生館は“教育”という現場から見つめています。
AIの言葉と、人間の“体温”
ある日の授業で、小学生の生徒が「ありがとう」という作文を書いていました。
何度も消しては書き直し、ようやく完成したのは、たった一行。
「お母さん、朝ごはんありがとう。」
その短い一文には、子どもの素直な心が宿っていました。
AIがいくら膨大なデータを使って「感動的な文章」を生成しても、この一行には敵わない。
なぜなら、その子の言葉には“生きた経験”があるからです。
AIは「共感の技術」を学び、人の感情のパターンを分析して文章を作ります。
しかし、人間が紡ぐ言葉には、失敗や痛み、迷いの時間が染み込んでいます。
それこそが、AIには再現できない“人間の体温”なのです。
共感の時代に起こる「共感疲労」
現代社会は「共感の言葉」であふれています。
SNSでは「あなたはそのままでいい」「頑張らなくていい」などの優しいフレーズが並びます。
どれも正しい言葉ですが、似たような表現が増えるほど、心が麻痺してしまうこともあります。
心理学ではこれを**共感疲労(compassion fatigue)**と呼びます。
人はあまりにも多くの“優しさ”に触れると、かえって疲れてしまうのです。
教育の世界でも同じ現象が起きています。
「励ます」「支える」という言葉が表面的に使われる一方で、
子どもたちの本当の心に届いていないケースも少なくありません。
大切なのは、“型にはまった共感”ではなく、一人ひとりの背景に寄り添う共鳴です。
「その子がどんな時間を過ごしてきたのか」を見つめたうえでかける言葉こそ、真に力を持ちます。
揺らぎがあるから、言葉は響く
AIの文章には迷いがありません。
けれど、人間の言葉はいつも少し不安定で、揺れています。
「もう無理かもしれない」
「でも、きっと大丈夫」
この“矛盾の間”にこそ、人間らしさがあるのです。
AIが論理的に「正しさ」を提示する一方で、
人の言葉は不完全でありながらも、感情を通じて人を動かす力を持っています。
教育の場で子どもが心を開くのは、完璧な先生ではなく、
悩みながらも一緒に考えてくれる先生です。
つまり、“共感”よりも“共鳴”が必要なのです。
AIが答える時代に、人は何を学ぶのか
AIが文章を作り、問題の答えを瞬時に出すようになった今、
私たち教育者が育てるべきは「正解を探す力」ではなく、問いを立てる力です。
「なぜそう思ったの?」
「その考えの背景には、どんな気持ちがあるの?」
こうした対話の積み重ねが、AIでは生み出せない“人間的な学び”を育てていきます。
聡生館では、AIを拒むのではなく、人間らしさを磨くための道具として活用しています。
AIにできることはAIに任せ、人にしかできない「思考」「共感」「表現」を育てていく。
それが、これからの教育の中心になると考えています。
言葉が人をつなぐ、未来へ
AIの言葉がどれほど整っても、
人はきっと「人の言葉」を求め続けるでしょう。
なぜなら、言葉は情報ではなく、心の証明だからです。
誰かを思いながら言葉を選び、
届くかどうかわからなくても書かずにはいられない。
その不器用な営みの中に、人間らしい温かさがあります。
教育も同じです。
正しさだけでなく、不完全さの中にある希望を伝えたい。
AIが“共感の言葉”を量産する時代だからこそ、
人間は“共鳴の言葉”を紡ぐ存在でありたい。
そして、その共鳴が次の世代の心に受け継がれていく。
それが、聡生館の考える「学びの未来」です。
関連記事
Category
カテゴリー
Archive
アーカイブ