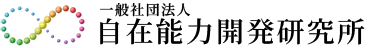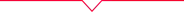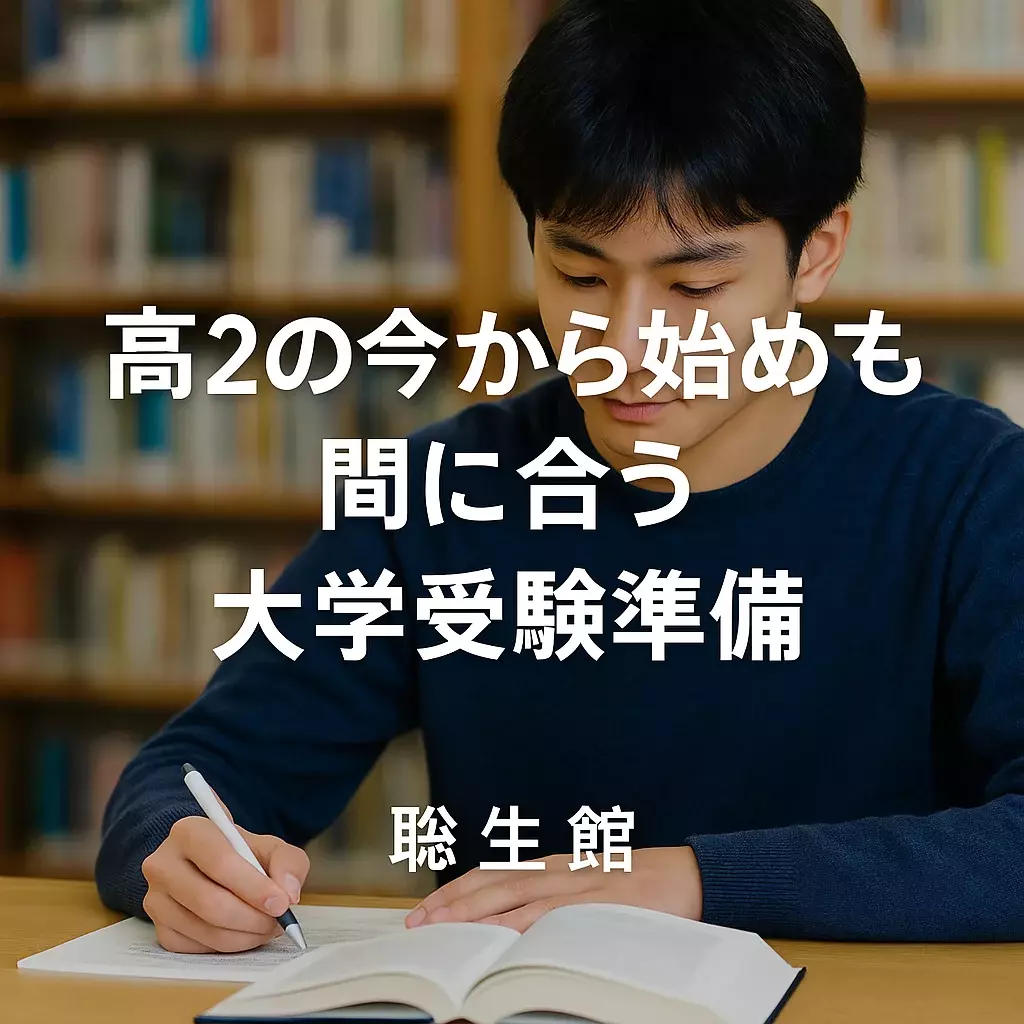
高校2年生のこの時期——
「受験はまだ先」「部活も忙しい」
そんな理由で、大学受験をまだ“自分事”として捉えられていない生徒は少なくありません。
しかし、冬が近づく今こそ、受験のスタートとしては実は遅すぎず、むしろ最適なタイミングなのです。
聡生館にも、毎年この冬に本気のスイッチが入り、そこから偏差値を大きく伸ばして志望校に合格した高3生が何人もいます。
今日は、「高2の冬から始めても間に合う理由」と、「ここから何をすべきか」を具体的にお伝えします。
1.「高2の冬」は、受験生としての“基礎づくり”のピーク
大学受験で最も重要なのは、基礎学力の完成度です。
英語なら
-
文法の理解
-
単語力
-
長文読解のベース
数学なら
-
教科書レベルの典型問題の定着
-
解法パターンの体系化
-
ケアレスミスを減らすための“数学的思考の整理”
国語なら
-
文章を構造的に読む力
-
論理的な読み取りの癖づくり
-
古典文法の知識
これらは「高3の春から一気に仕上げる」ことはできません。
高2の冬こそが、基礎力を固める最後のチャンスなのです。
2.今から始めても間に合う理由
理由①
“伸びる生徒”は、高2冬から高3夏までの伸びが最も大きい
過去20年以上の指導経験でも、もっとも成績が伸びる時期は
高2の冬 → 高3の夏です。
この半年間で、
-
偏差値50 → 60
-
偏差値55 → 65
といった“跳ね”が起こりやすい。
なぜか?
それは、この時期の学習が、丸暗記ではなく“思考力”の土台を作る学習になるからです。
理由②
入試は“基礎問題の集合体”だから
難関大学の問題も、実は
基礎+応用の組み合わせです。
たとえば英語長文も
-
単語が分かる
-
文構造が取れる
-
段落の関係が読める
この3つの“基礎動作”ができれば、大きく解けるようになります。
理由③
「高3から本気」は実は遅いから
高3生になってから
「間に合わない……」
「基礎が抜けているのに、応用ばかり解いてしまう」
という悪循環に陥る生徒は多いもの。
だからこそ、高2の今、
最初の一歩を踏み出せるかどうかが、大きな分岐点になります。
3.高2の今すぐやるべき“3つのこと”
① 英語の基礎完成(単語+文法+構文)
受験生の“伸び”は英語で決まります。
-
単語は1800語レベルを冬までに完成
-
文法は1冊を繰り返す
-
構文は長文読解の前提として必須
これを高2冬までにやると、高3春からの伸びがまったく違います。
② 数学は「典型問題の反復」で土台を固める
数学は、
パターン学習 → 思考整理 → 応用へ
という流れが絶対です。
今やるべきことは、
「青チャートの例題レベルを確実に解けるようにする」
ただこれだけ。
これを冬に始めると、高3夏に応用問題へスムーズに移れます。
③ 国語は“読解の型”を身につける
国語はセンスではなく技術です。
-
指示語が何を指すか
-
キーワードの扱い
-
主張と根拠の関係
-
比喩・抽象化の読み分け方
この“読みの型”を冬に身につけておくと、現代文の正答率が安定します。
4.“ここから伸びる”ための聡生館の学習サポート
聡生館では、冬期講習から高2生の受験準備を本格的にスタートしています。
● 1対3~4の個別指導+代表による直接指導(受験生)
高2冬の段階から、
-
必要な基礎
-
苦手の原因
-
伸ばすべき科目
を1人ずつ徹底分析します。
● 高2 → 高3へ向けた「半年の学習設計」
学習計画は“無理なく・でも確実に”伸びる設計にします。
-
英語単語の到達度
-
数学の範囲と定着度
-
読解力の現状
-
苦手の根本原因
これを分析し、「半年でどこまで上がるか」を示します。
5.高2冬の行動が、未来を決める
結局、一番大切なのは
“始める勇気を持つこと”
です。
大学受験にフライングはありません。
むしろ、
高2の冬こそが最も結果につながりやすい“黄金の時間”。
ここで一歩踏み出せた生徒は、例外なく受験生として強くなります。
最後に —— 迷っているなら、今がチャンスです
もし、
「このままでは不安」
「何から始めていいかわからない」
と思っているなら、
今こそ動き出す絶好のタイミングです。
聡生館では、冬期講習(12/26開校)に向けて高2生の受講相談を受付中です。
-
まずは無料体験授業(2週間)
-
現状分析テスト
-
個別学習計画の作成
受験準備を、本気でスタートできる体制を整えています。
あなたの“今から”の一歩が、未来の合格をつくります。
ぜひ早めにご相談ください。
-
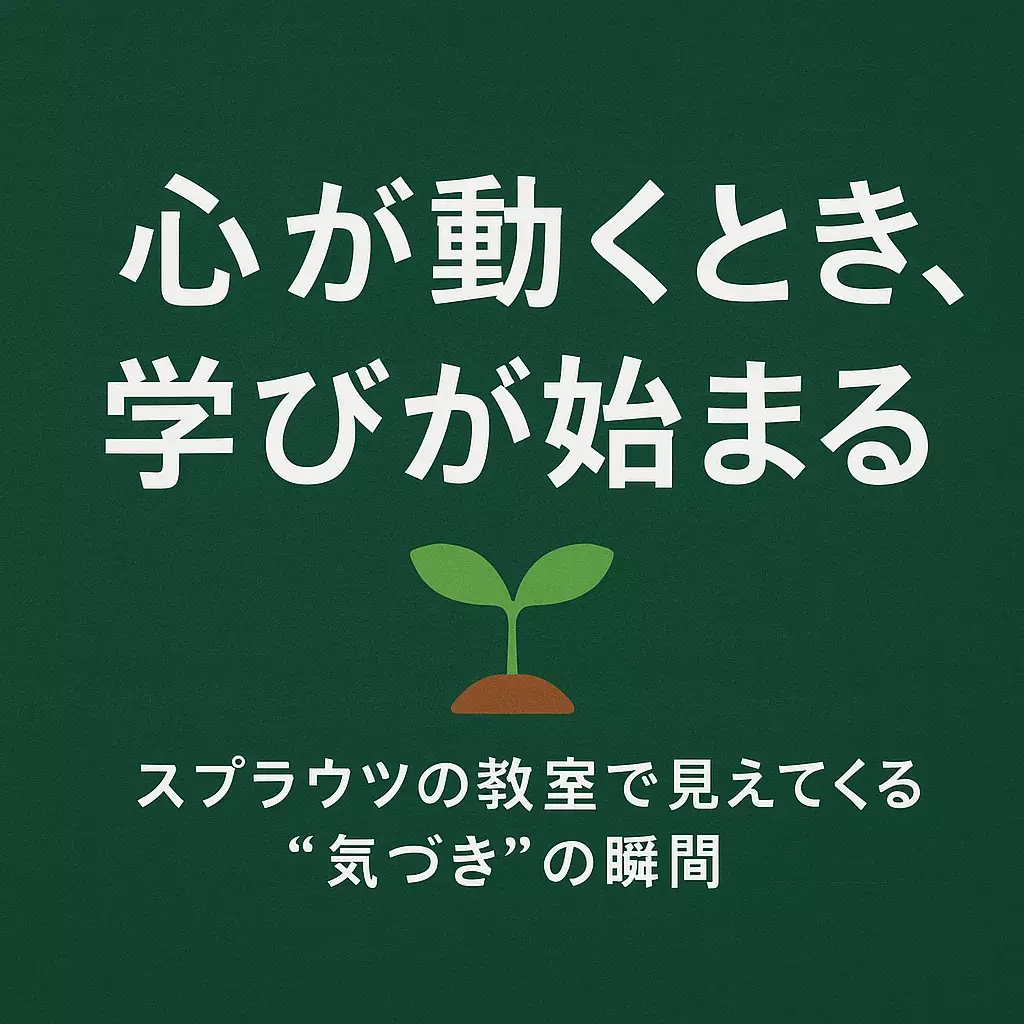 スプラウツ心が動くとき、学びが始まる — スプラウツの教室で見えてくる“気づき”の瞬間 —2025/10/27
スプラウツ心が動くとき、学びが始まる — スプラウツの教室で見えてくる“気づき”の瞬間 —2025/10/27 -
 聡生館小中高生のGWの初日、1名を除きいつも通りに通塾してきました。2025/04/29
聡生館小中高生のGWの初日、1名を除きいつも通りに通塾してきました。2025/04/29 -
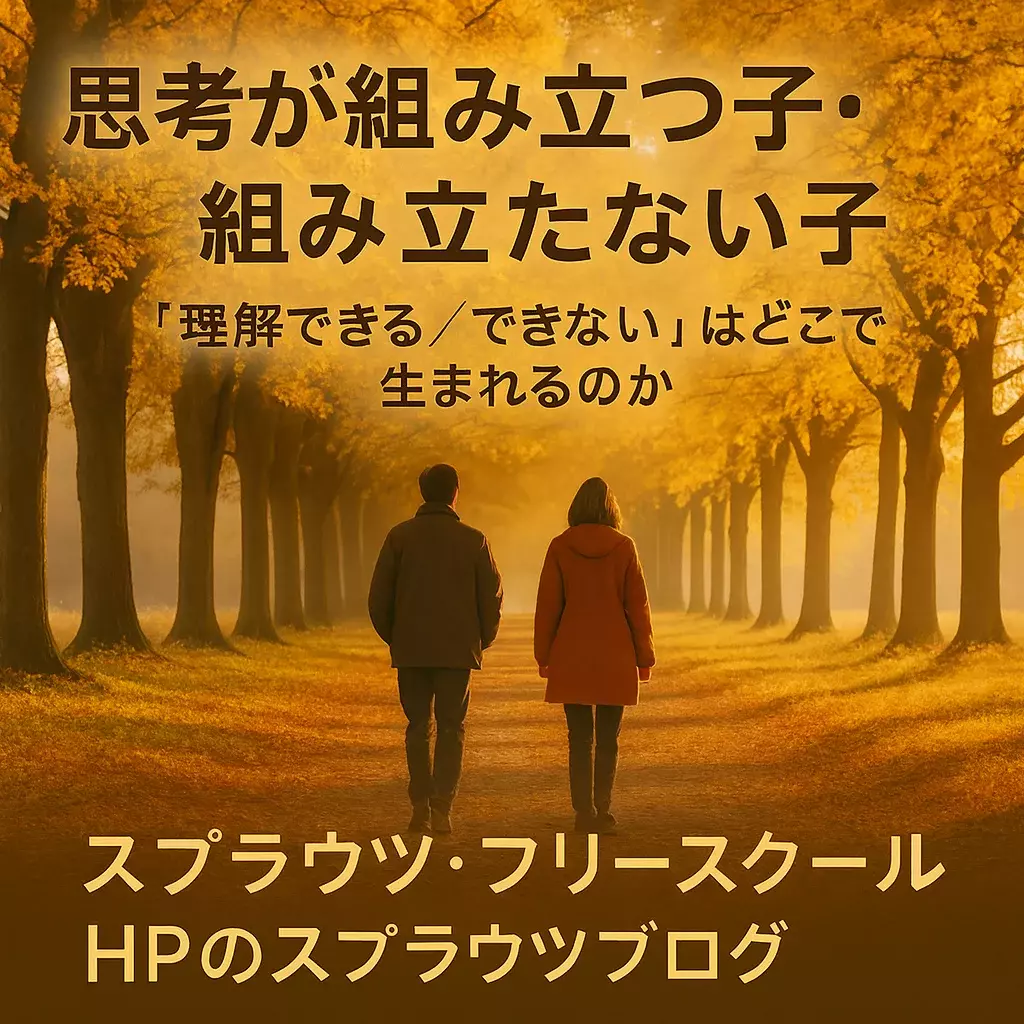 スプラウツ思考が組み立つ子・組み立たない子 ――算数の“つまずき”はどこから生まれるのか2025/11/15
スプラウツ思考が組み立つ子・組み立たない子 ――算数の“つまずき”はどこから生まれるのか2025/11/15