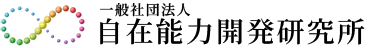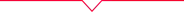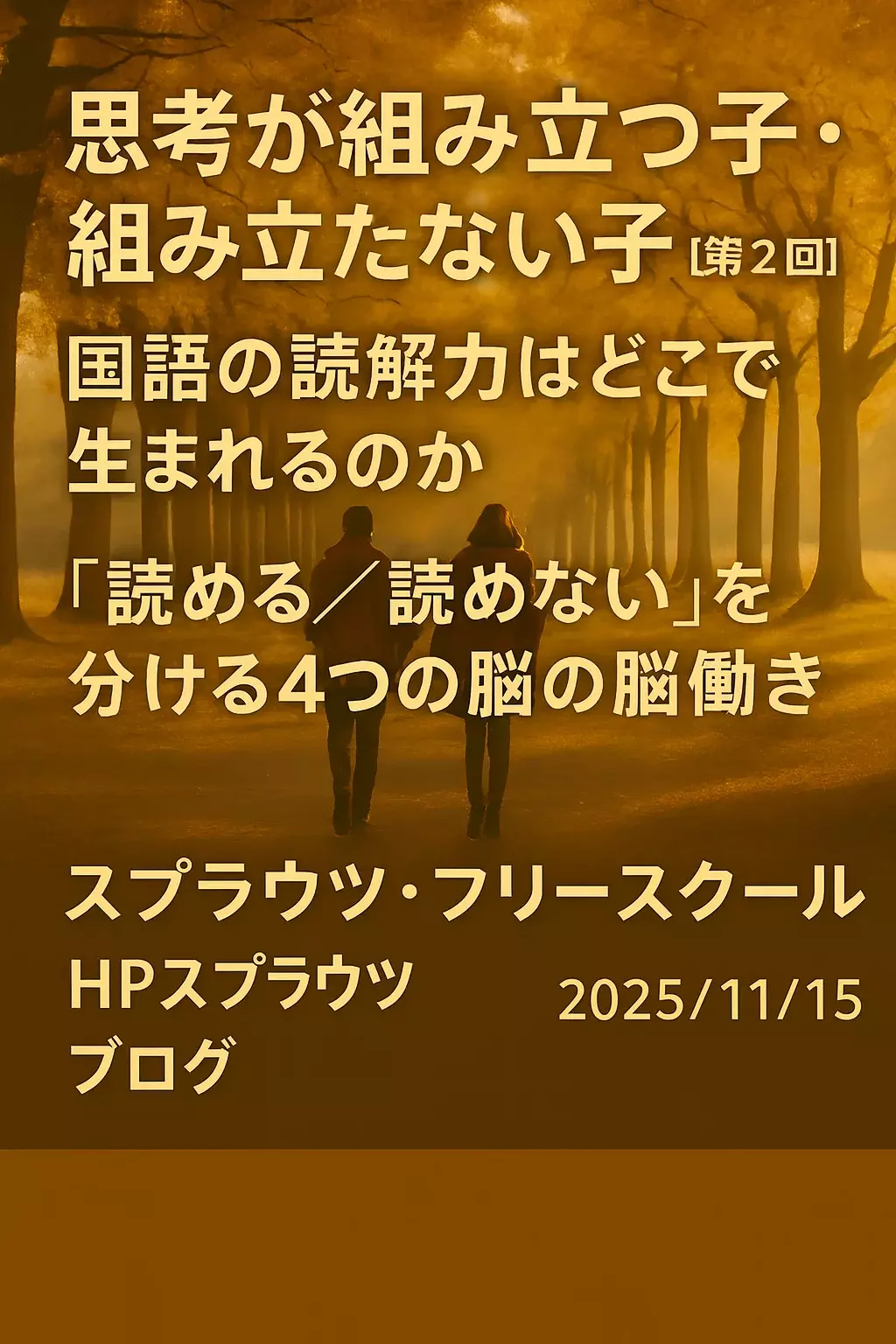
学校や家庭で「文章が読めない」「国語の問題が解けない」と悩む子どもは少なくありません。
特に、スプラウツに相談に来られる保護者の方からは、
-
読んでも内容が頭に入ってこない
-
本文のどこを読めばいいのかわからない
-
指示語(これ・それ)がつかめない
-
問いの意図と本文が結びつかない
といった声がよく届きます。
しかし、読解力の差は“生まれつき”の能力ではありません。
実際には、文章を理解する際に働く 4つの脳の機能 の違いが、子どもたちの読解力に大きく影響しています。
本記事では、その4つの働きをわかりやすく解説し、読解力を伸ばすためにできる実践方法をご紹介します。
■1.読解力の差は何から生まれるのか?
「文章が読めない」というと、語彙力の問題や読書量の不足が原因だと思われがちです。
ですが、読解のつまずきの根本には、もっと“認知的なメカニズム”があります。
文章を読むとき、脳は次のような作業を同時に行います。
-
文の意味を理解する
-
直前の内容を保持する
-
文脈と照合する
-
全体の構造を把握する
-
筆者の意図を推測する
どれか一つでも弱いと、読み進める途中で混乱したり、文章全体が「バラバラの情報」になってしまいます。
■2.読解力を支える4つの脳の働き
① ワーキングメモリ(作業記憶)
ワーキングメモリとは、読んだ内容を一時的に頭に保持しながら、次の文と照らし合わせる力のことです。
この力が弱いと、
-
指示語(これ・それ)が何を示すかわからない
-
読んでいる途中で話がつながらなくなる
-
前後関係がつかめない
といった困難が生じます。
特に、不登校やストレスのある子どもは、この機能が一時的に低下する傾向があります。
② 構造把握力(チャンク化)
読める子は、文章を次のような “まとまり” で捉えています。
-
主張
-
理由
-
具体例
-
結論
この構造が見えると、文章は「流れ」として理解できます。
読めない子は、文章を“一文ずつ”読んでしまい、全体がつながりません。
構造把握力は、読解の核心となる力です。
③ 語彙ネットワーク(意味のつながり)
語彙とは、ただ知っている言葉の量のことではなく、
言葉と言葉の意味がどれだけ“つながっているか” の問題です。
語彙ネットワークが弱いと、
-
少しむずかしい単語に出会うだけで読解が止まる
-
文脈から意味を推測できない
-
抽象的な内容がつかみにくい
という状態になります。
読書体験や日常の会話が、このネットワークを育てます。
④ 筆者意図を読み取る認知力
文章はただ情報が並んでいるのではなく、筆者には必ず「意図」があります。
読める子は、
「なぜここで例を出したのだろう?」
「筆者が一番言いたいのはどこか?」
と、意図を追いながら読み進めています。
読めない子は、文章を“情報の列”として読んでしまい、本質がつかめません。
■3.読解力は後から必ず伸ばせる
読解力は“才能”ではありません。
4つの脳の働きはいずれも 後から育てていくことができる力 です。
スプラウツでは、以下のステップで読解力を伸ばす支援を行っています。
●① 構造化(図解・色分け)
段落ごとに
-
主張
-
理由
-
例
-
結論
を色や形で整理し、“文章の地図”として視覚化します。
●② 要約トレーニング
一段落一文の要約や、短い文章からの要点抽出を行います。
要約は、文章の本質をつかむための強力な訓練です。
●③ 指示語を追う練習
「それ」「このため」などの指示語が示す内容を線で結ぶだけでも、文章の構造が見えてきます。
●④ 語彙ネットワークを広げる読書
特別な本でなくても構いません。
子どもが興味を持つ分野を中心に、言葉の世界を広げていきます。
多様なジャンルへの接触が語彙ネットワークを育て、読解力の基盤になります。
■4.不登校の子にこそ必要な「思考の組み立て直し」
不登校や学びに不安を抱える子どもは、
「自分はできない」という自己イメージを持ってしまうことがあります。
しかし実際には、
できないのではなく、脳の思考の使い方が一時的にうまく働いていないだけ
ということが多いのです。
安心できる環境で負荷を調整しながら学び直すことで、
思考の柔軟性は必ず回復します。
読解力を回復させることは、
子どもが再び学びに向かうための大切なステップです。
■まとめ
国語の読解力は、“才能”ではなく、
-
ワーキングメモリ
-
構造把握力
-
語彙ネットワーク
-
筆者意図の理解
この4つの認知機能の組み合わせによって決まります。
そして、これらはどの子も育てることができます。
スプラウツは、子どもたちが
「読める」「わかる」という感覚を取り戻し、
学びと心のバランスをもう一度整えていくための場です。
ゆっくり、ていねいに。
そして確実に、読み解く力を育てていきましょう。
by Dr. Kazushige.O
一般社団法人自在能力開発研究所 代表理事
スプラウツ 代表
-
 聡生館今日から「学童型夏休み宿題大作戦」の生徒さんが出席し始めました。これからのお申込みも未だ可能です。2025/07/29
聡生館今日から「学童型夏休み宿題大作戦」の生徒さんが出席し始めました。これからのお申込みも未だ可能です。2025/07/29 -
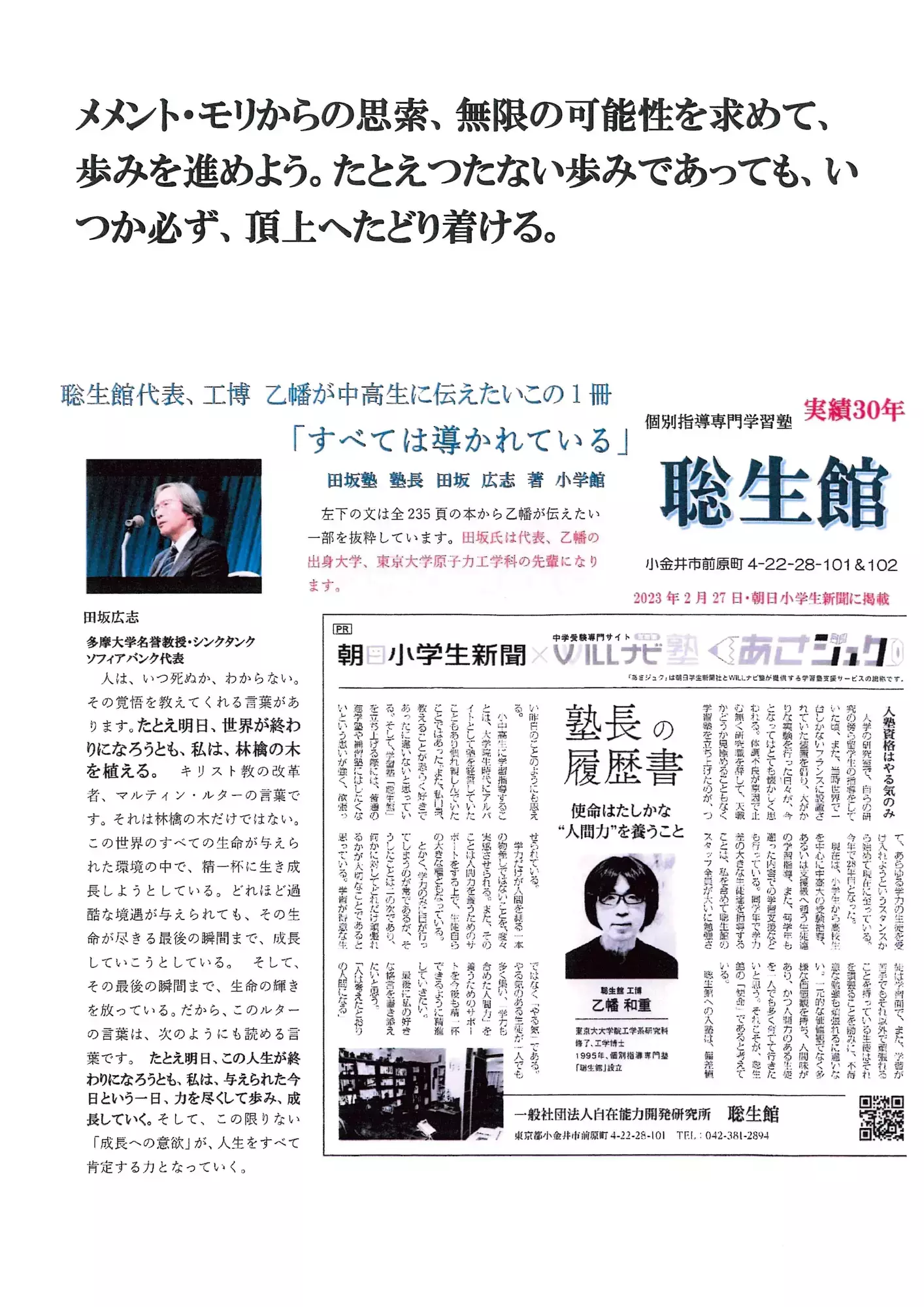 聡生館学習意欲はどうやって保つことができるのでしょうか。2025/07/06
聡生館学習意欲はどうやって保つことができるのでしょうか。2025/07/06 -
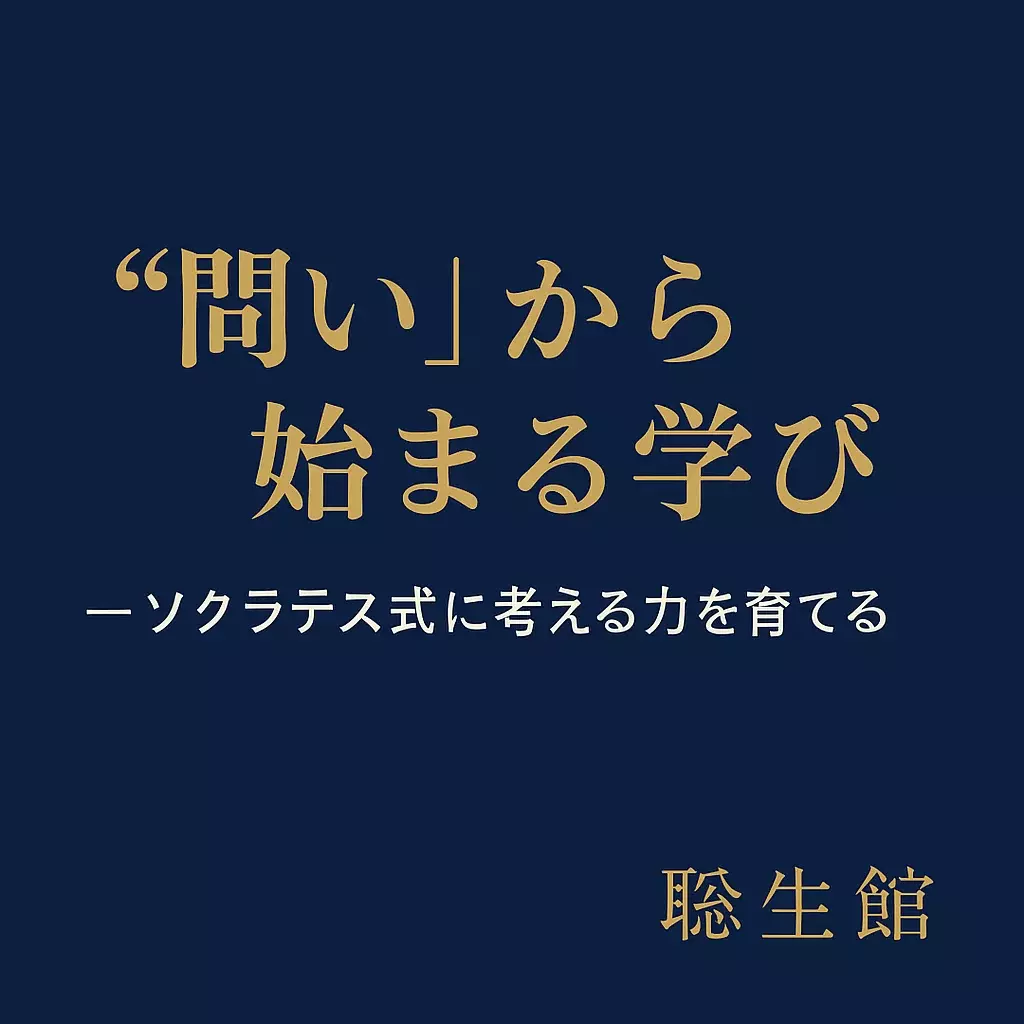 聡生館“問い”から始まる学び — ソクラテス式に考える力を育てる —2025/10/21
聡生館“問い”から始まる学び — ソクラテス式に考える力を育てる —2025/10/21